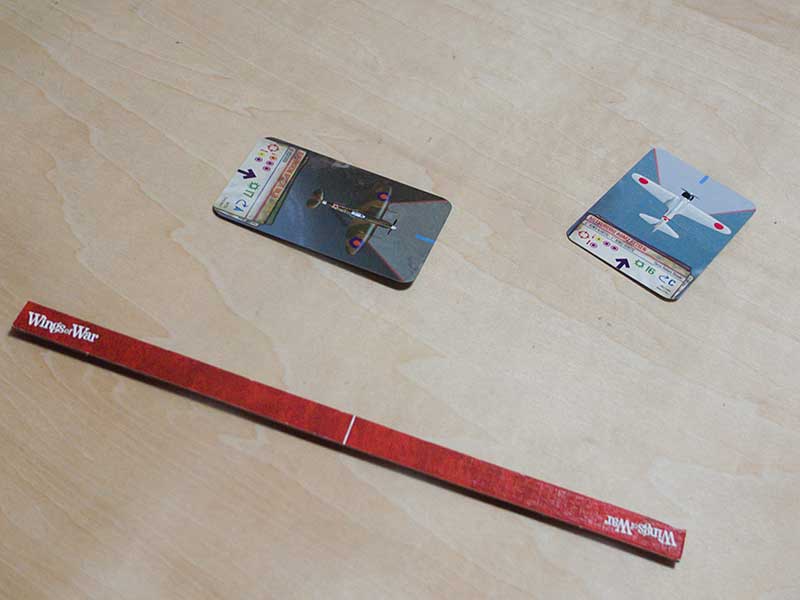K藤氏の自宅ゲーム会に参加しました。参加者5人。
7 Wonders (Repos)・The Republic of Rome (Valley Games)・Fab Fib (Kidultgame)・Lupusburg (daVinci Games)・Safranito (Zoch)をプレイしました。
まずは同人ゲームのテストプレイから。以前テストしたハロウィンテーマのゲームの新バージョンですが、システムががらっと変わってかなり遊べるものに仕上がってました。
7不思議は5人プレイだとほとんどのカードが一期一会で作戦も何もあったものではありませんが、カードの組み合わせで得点が大きく変動する緑カードの重要度が高くなるのかな、という感じを受けました。
共和制ローマは初期共和制シナリオを。5人だとほとんどの投票で最後の投票者がキャスティングボードを握ることになるので、俄然選挙ゲームらしくなります。ただ、初期共和制ではポエニ戦争の処理が最大の難問としてローマに襲いかかるので、あまり陰謀を巡らせる余裕はありません。ポエニ戦争とマケドニア戦争の両立はとても可能な話ではなくローマは滅亡しました。
ファブフィブはカウントアップ系のバーストゲームっぽいブラフゲーム。正直に申告するときはノータイムで宣言できるので、テンパってくるとついついルール上言えないコールが口から溢れてしまい、簡単に見破られてしまいます。正直者には全くもって向きません。
ルプスブルグは人狼を少人数向けカードゲームに再設計したゲーム。人狼からの最大の変更点は、各プレイヤーにキャラクターが2人ずつ配られ、2人とも死んだら脱落というところです。村人が勝ったときは別途得点を計算して勝敗判定をするので、脱落していても勝てるチャンスがあります。
狼男(絵は見るからに狼オカマですが)担当だったのですが、ほとんど情報がない最初の民衆裁判でいきなり狼が処刑されてしまいました。これで逆に村人のマークから外れてしまったらしく、残ったもう一方で最後の3家族までなんとか生き延びることができましたが、さすがに最後まで騙しきることはできませんでした。
1人減って最後はサフラニート。スパイスを競りで買って特定の組み合わせを作るのが目的ですが、競りの方法が競り値の書いてあるチップをおはじきのように弾いて、当たったところのスパイスを順にその価格で買うという豪快なシステム。全力で高額ビッドをしても全然希望と違うスパイスが買えてしまうという怪作です。
全員2つずつレシピを完成させ勝利まであと1枚というところで、完全に外れていたチップがたまたま他のプレイヤーに弾き飛ばされてまさに必要だったスパイスの枠に飛び込んで勝っちゃいました。